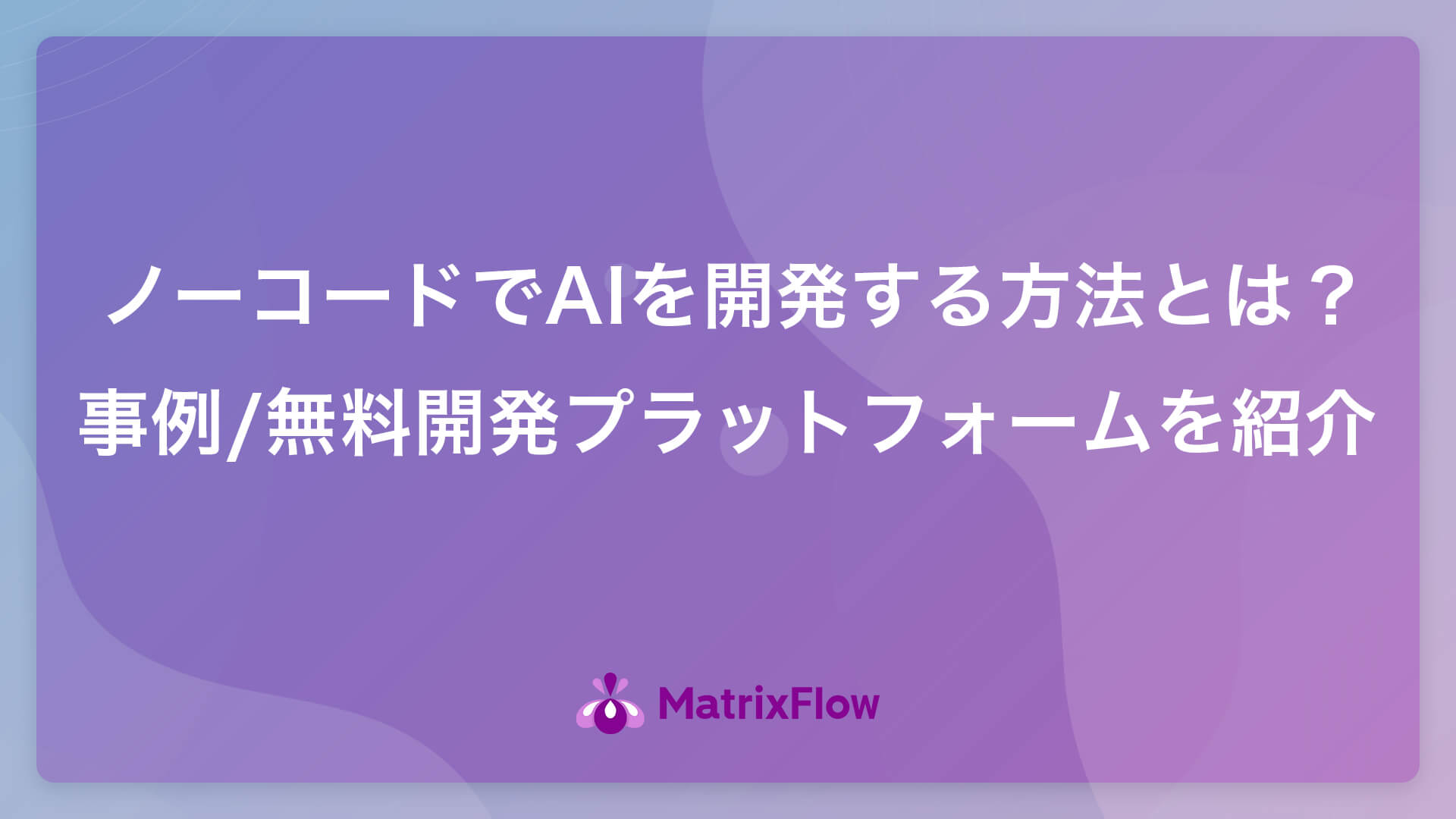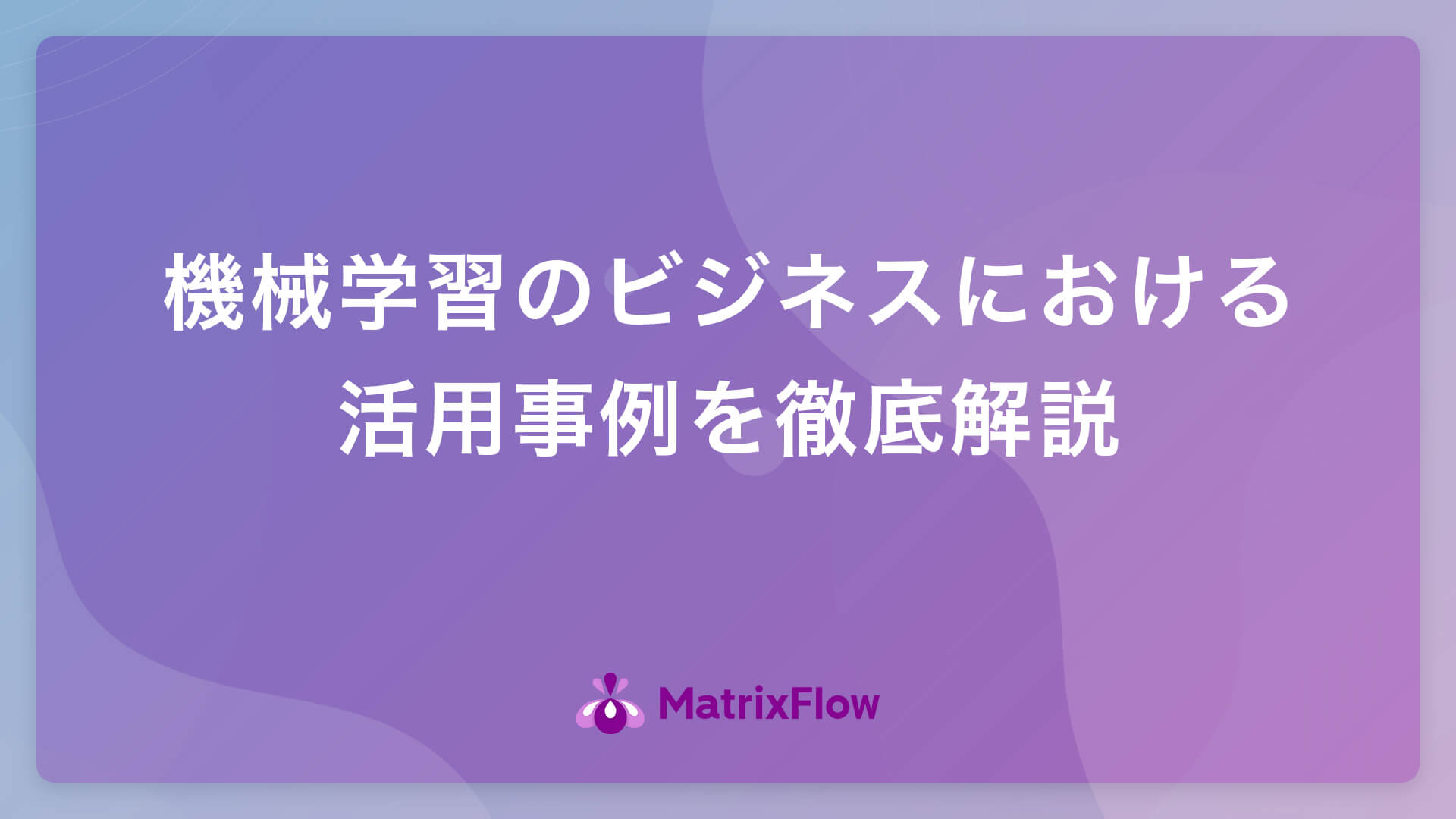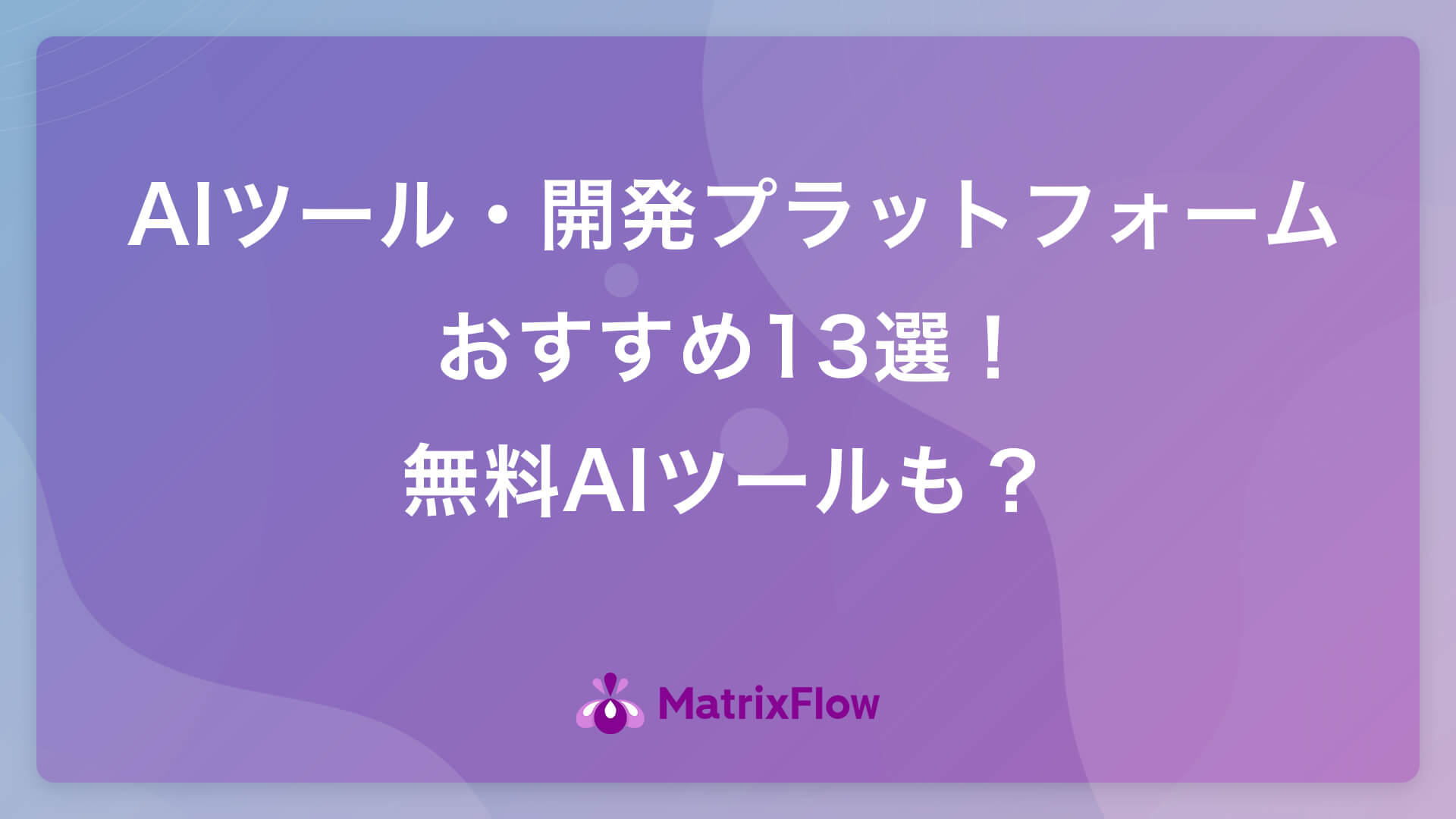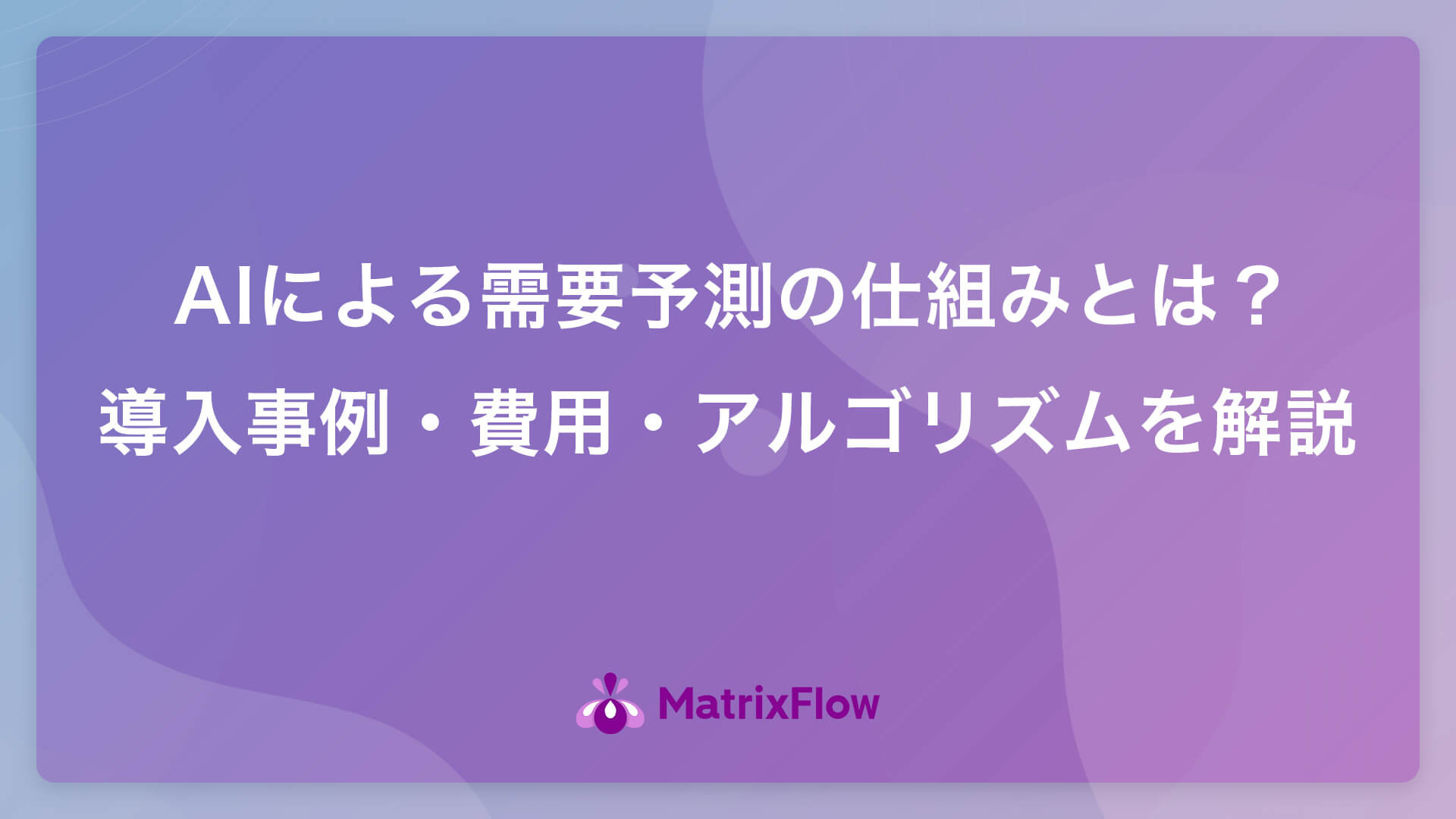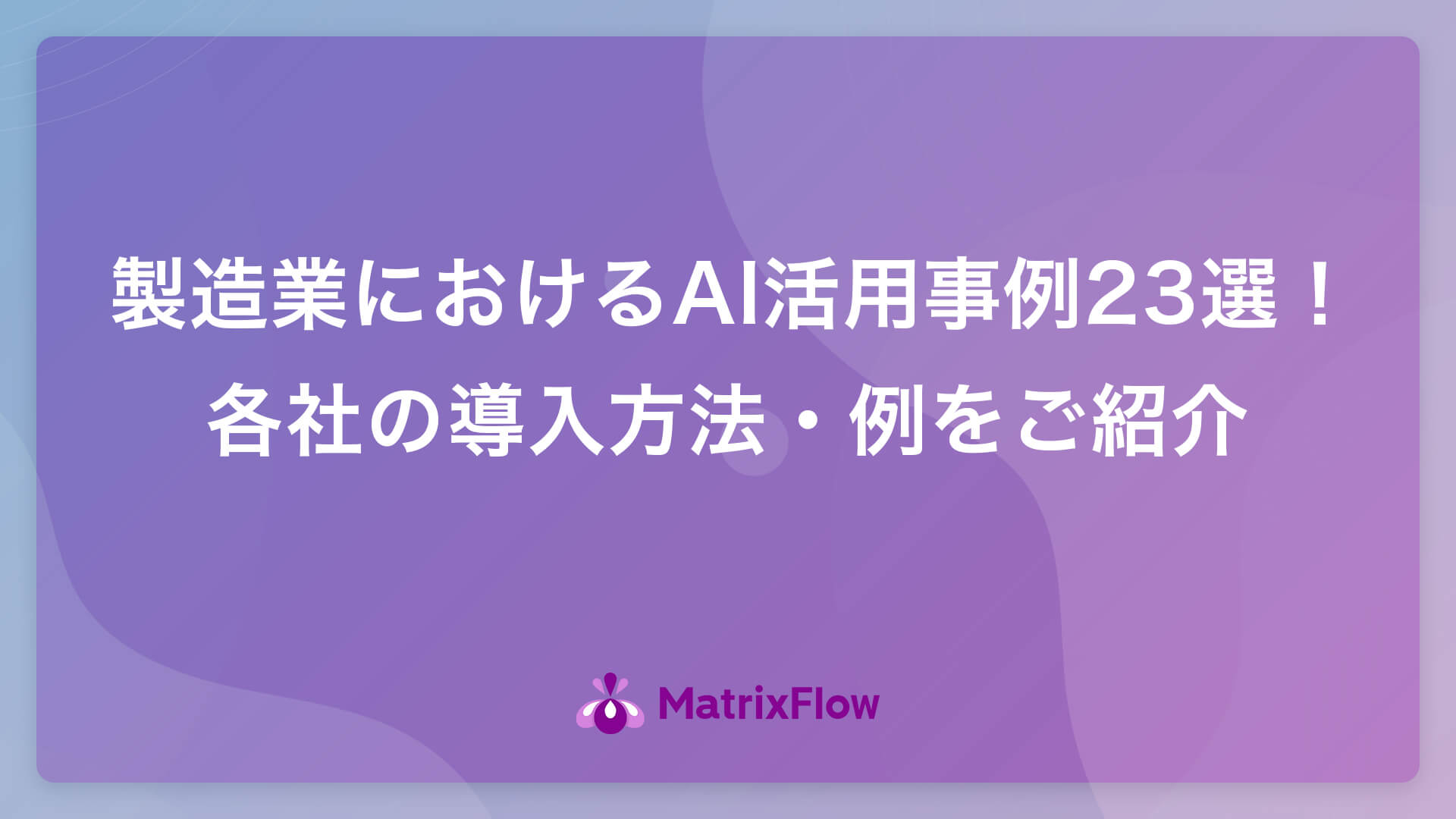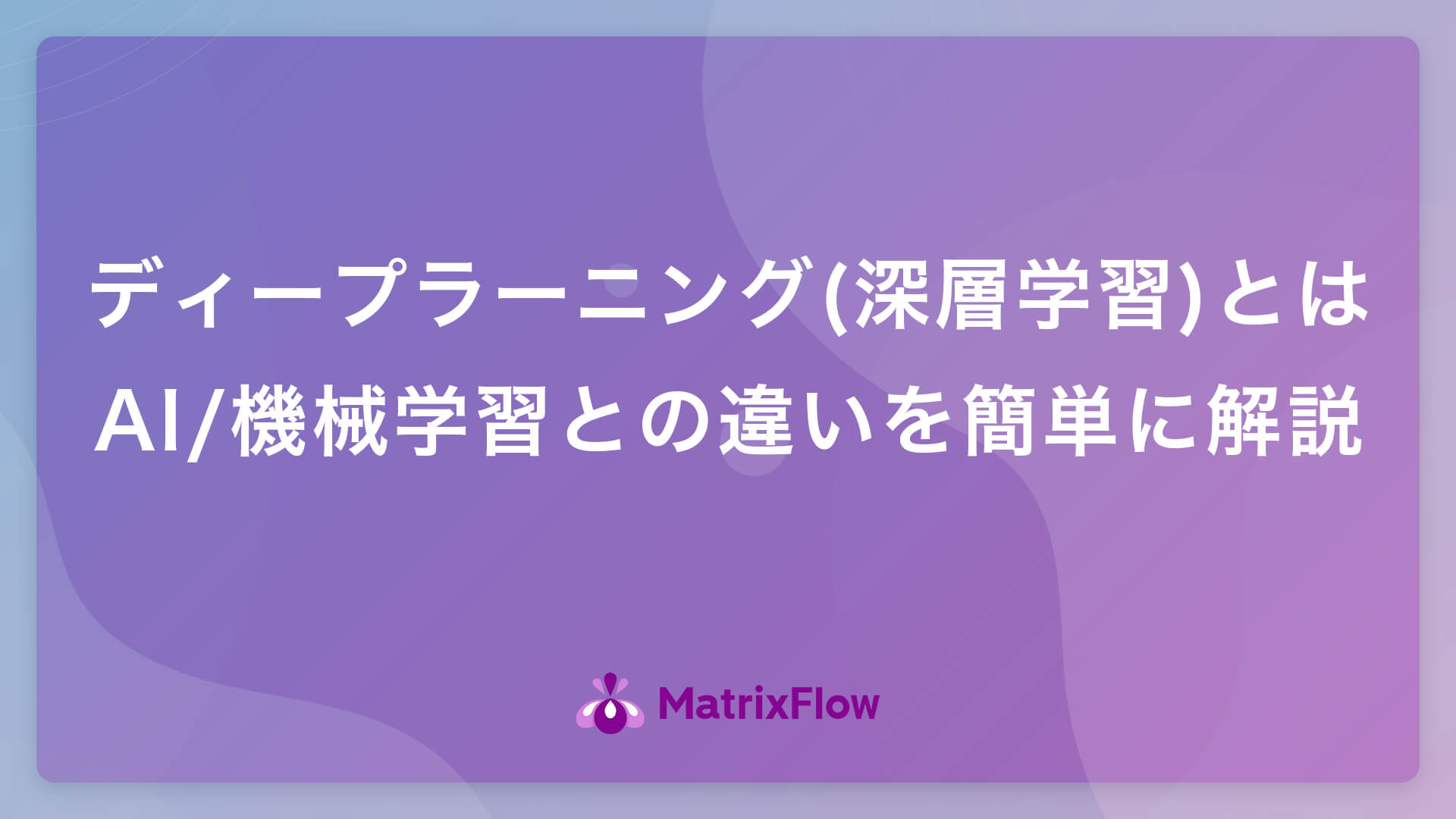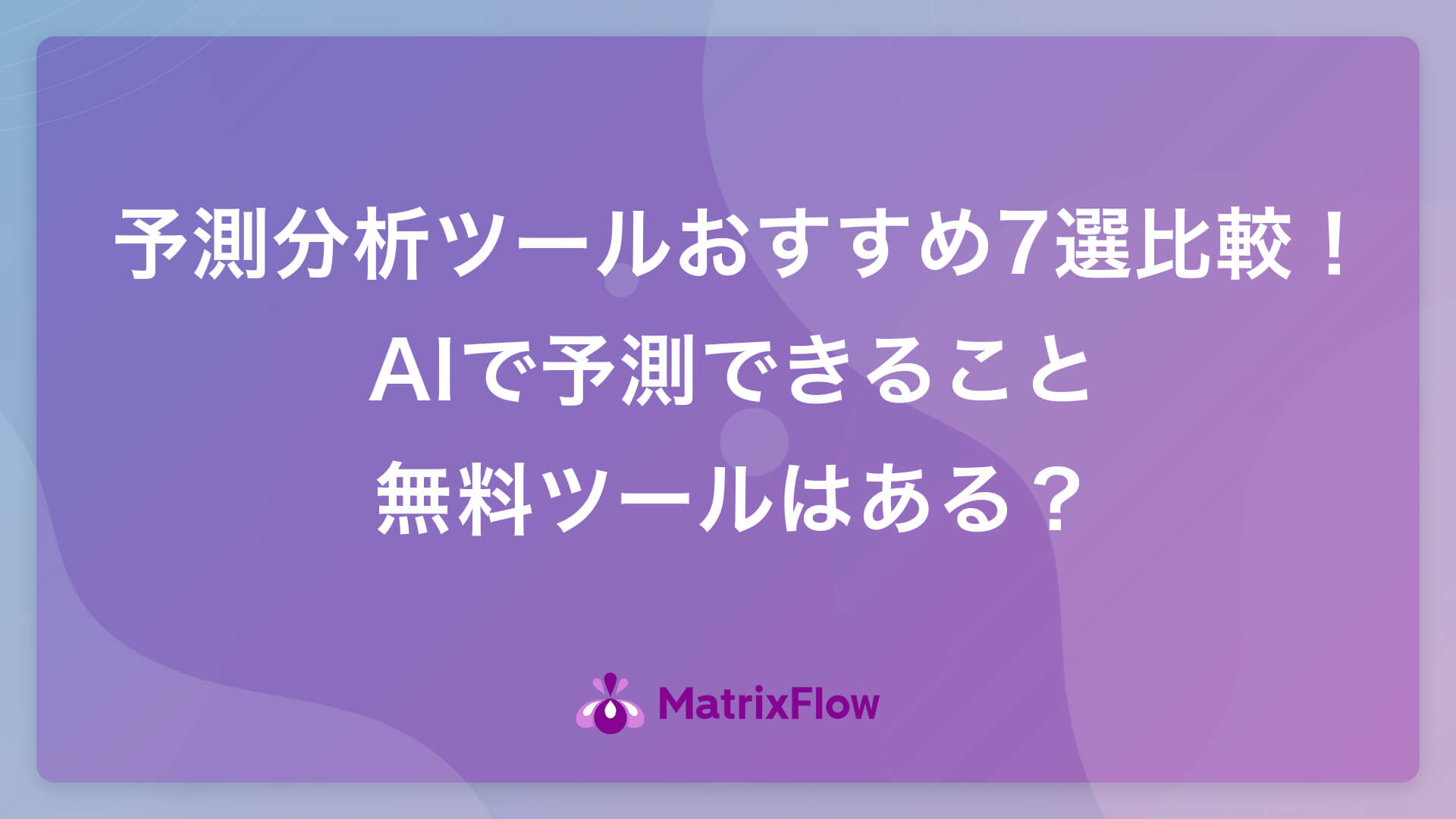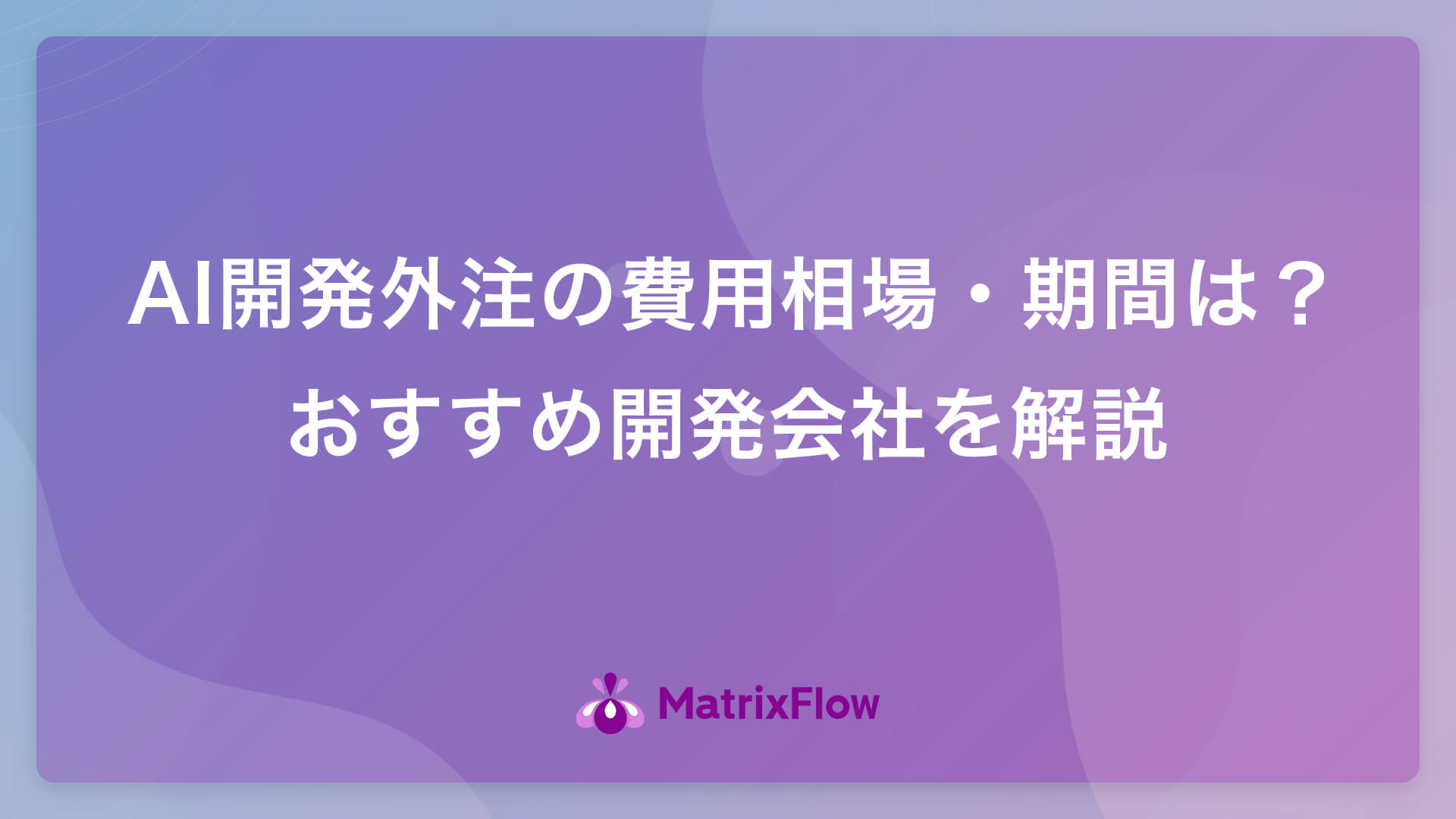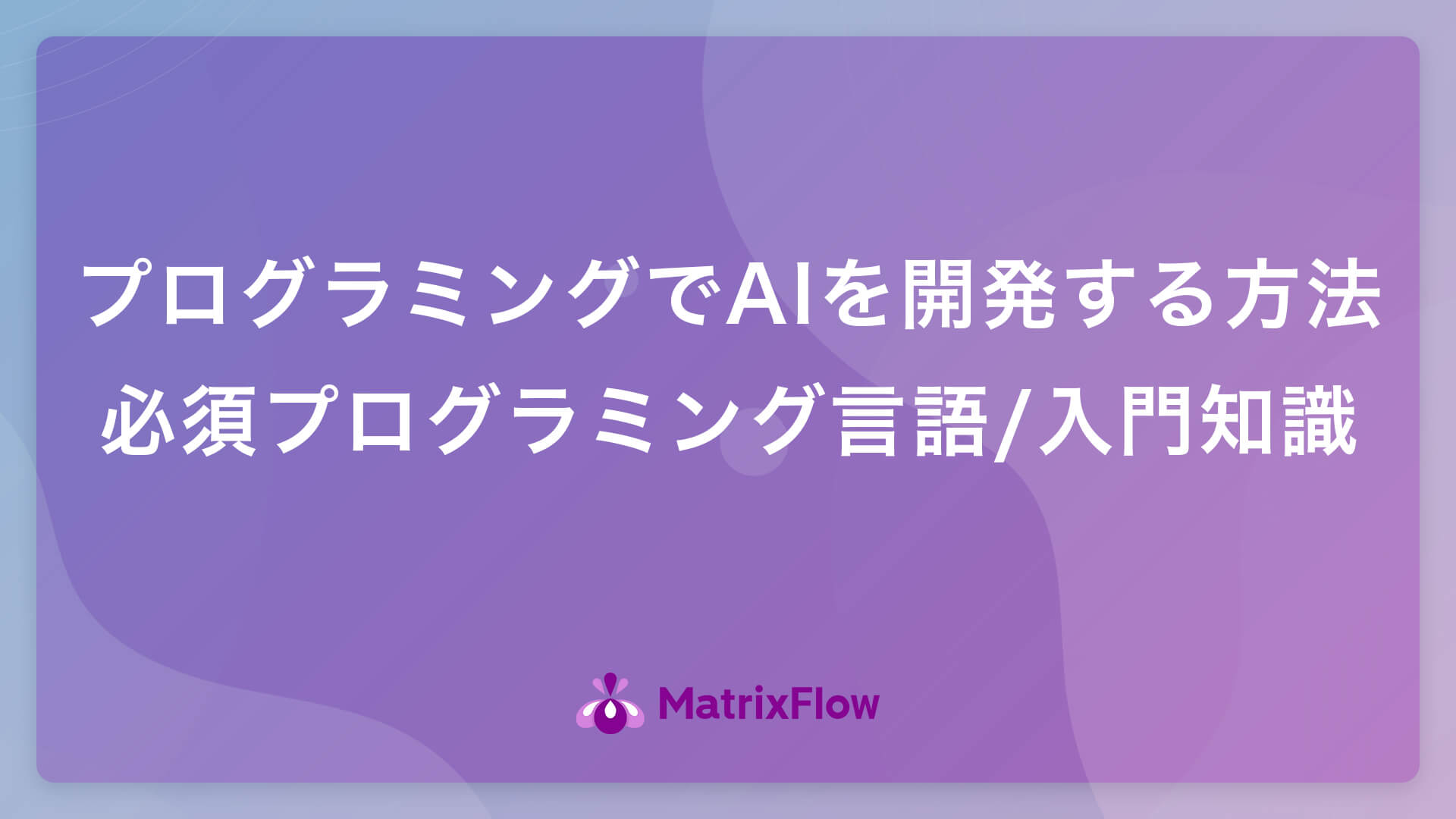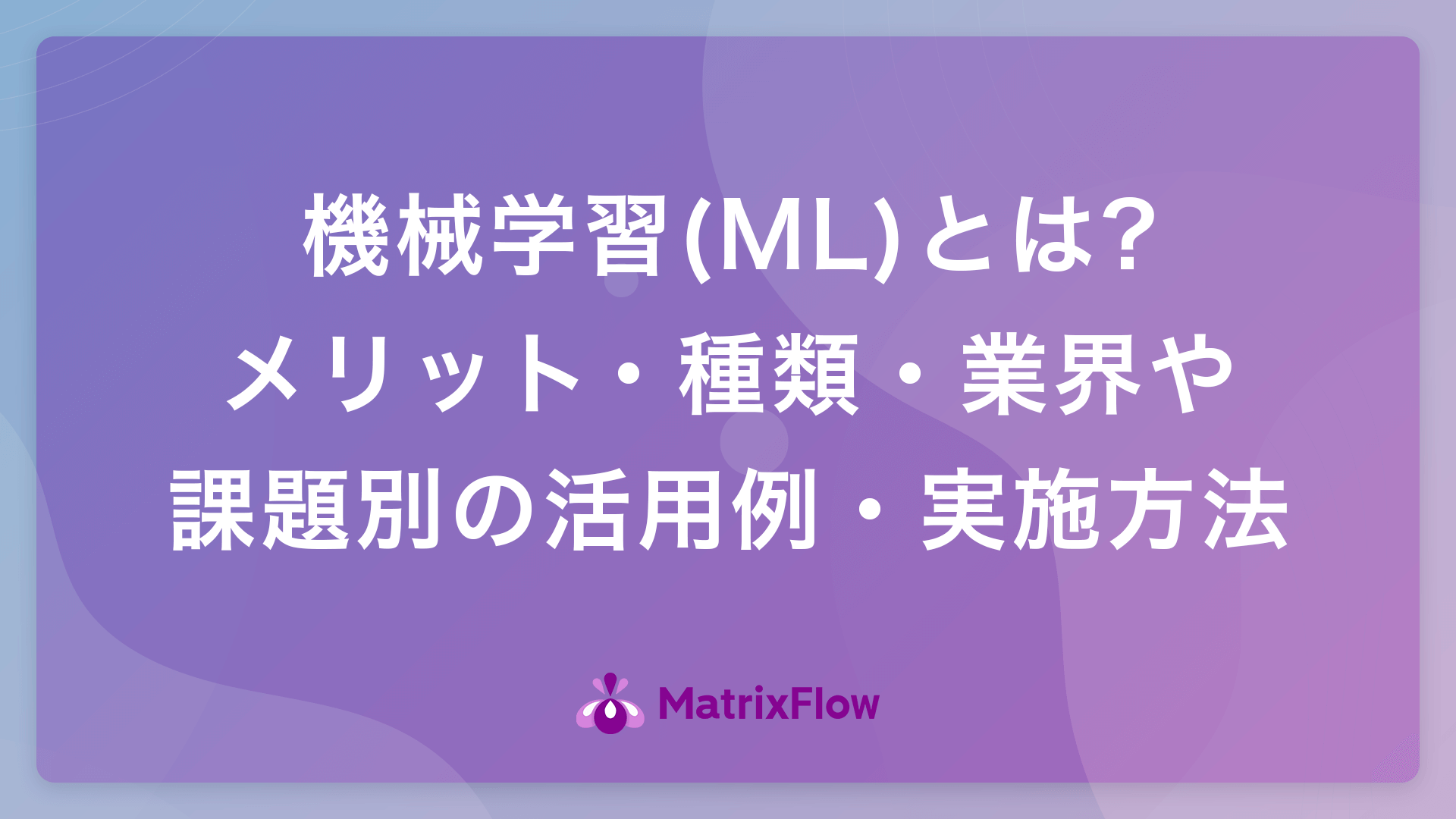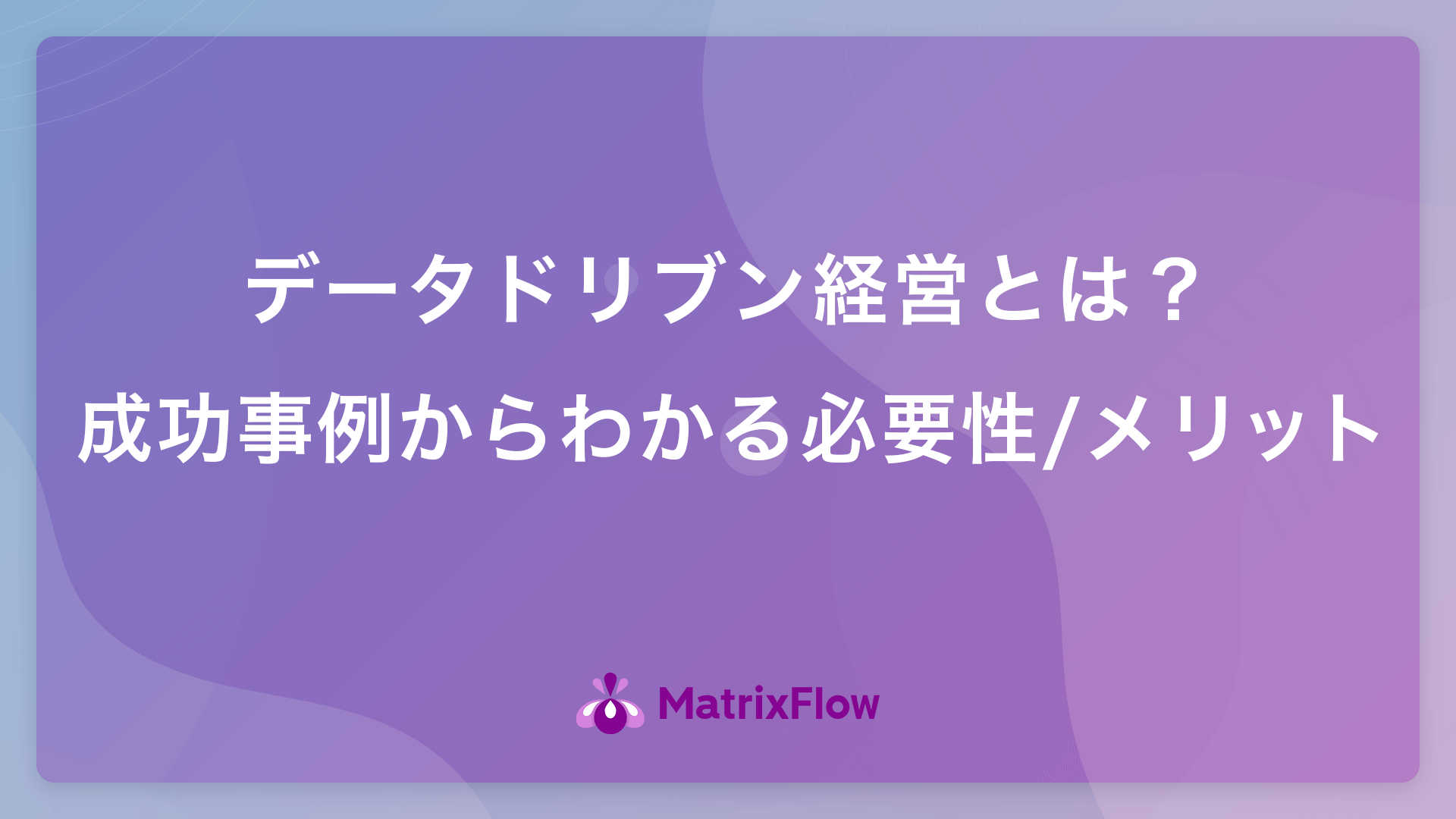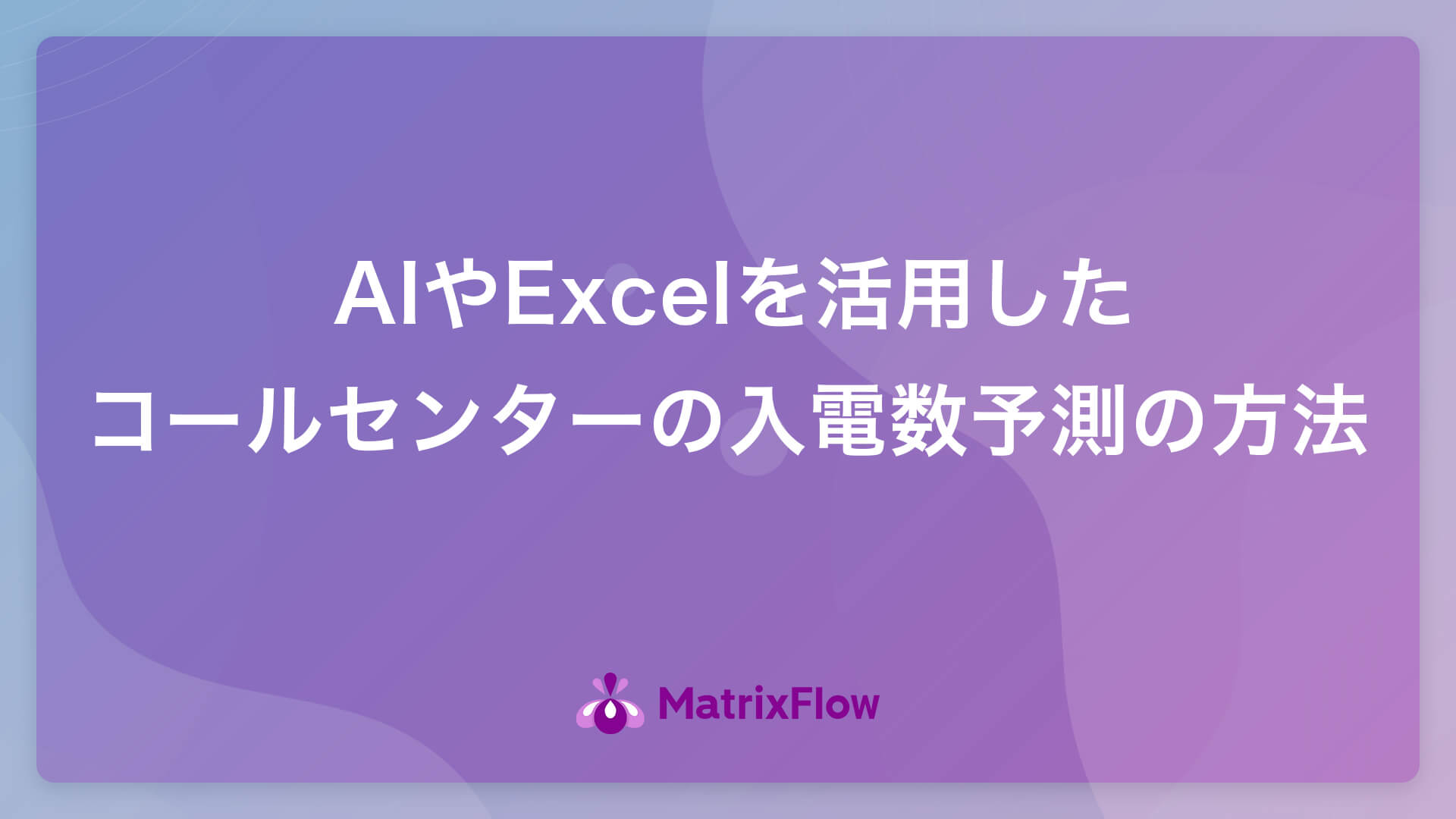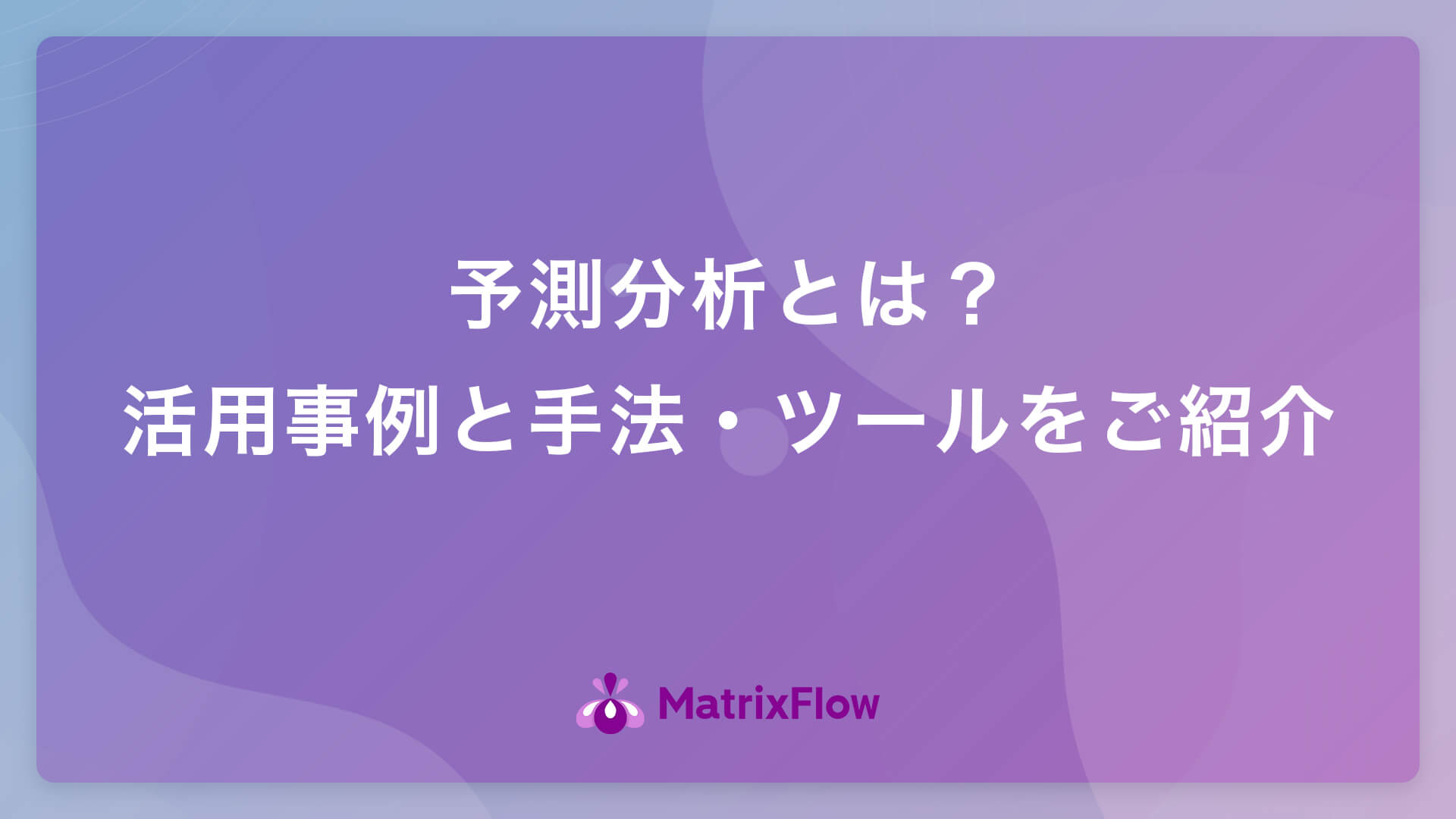AIを活用した採用予測 – 実例・方法をご紹介!
「苦労して採用した人が1ヶ月で辞めてしまった」 「求めているスキルと実際の働きぶりに差があった」 こうした悩みを持たない採用担当者は、いないといっても過言ではありません。 要件にマッチした人材の採用は、どの会社においても重要課題です。 採用のマッチング率向上への期待から、人材採用にAIを活用する動きが見られています。 AIを活用することで要件に合った人材採用ができるだけでなく、採用工数を大幅に削減できます。 どのように採用領域でAIを活用するのか、具体的な事例と共に解説していきます。
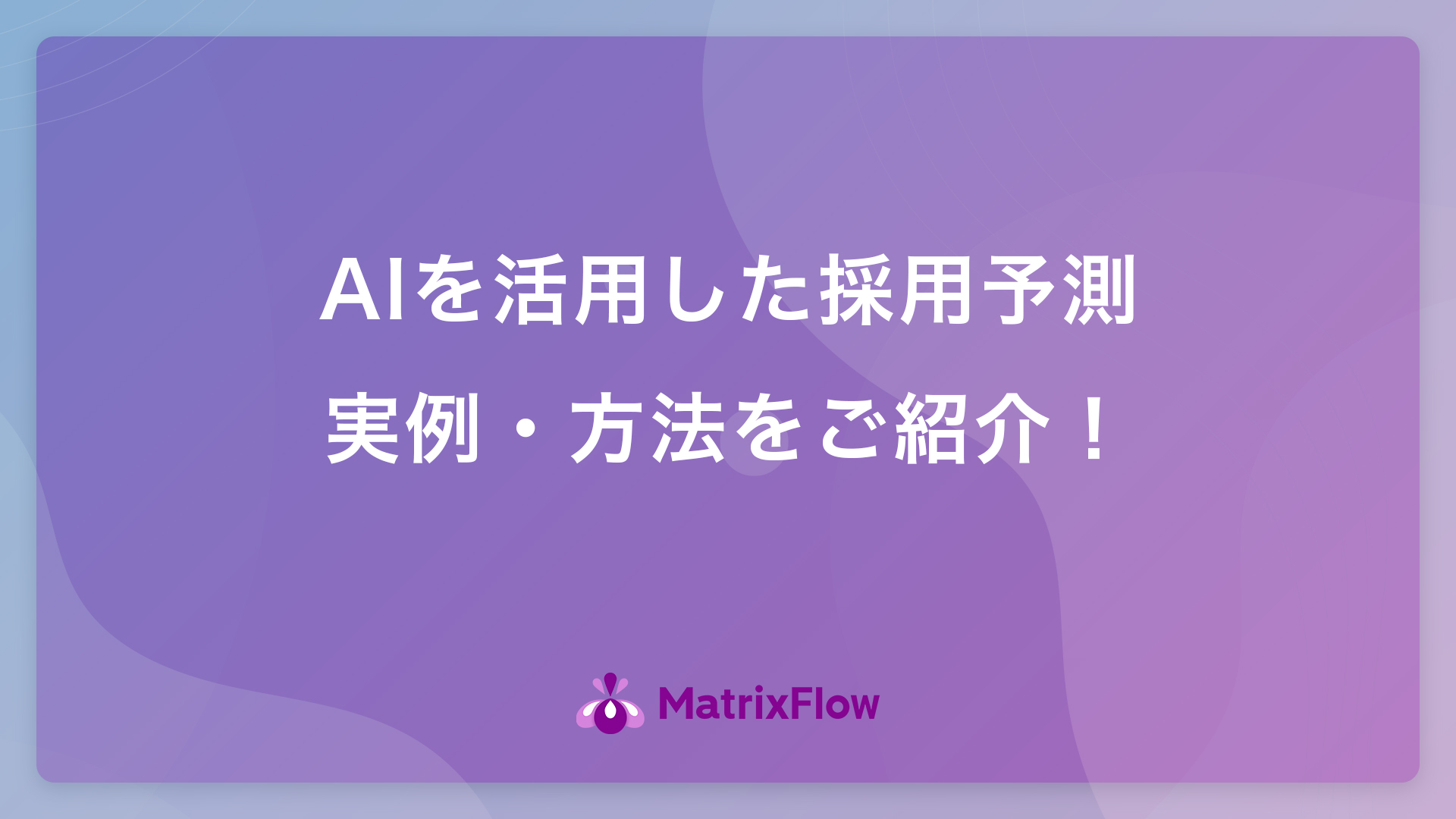
-
AIを活用した採用予測とは?
そもそも、AIを使った採用とはどのようなものなのでしょうか。
採用領域でAIを活用する方法はいくつかありますが、現在最も導入されているのは書類選考です。
書類選考の段階でAIを使い、候補者の絞り込みをするというものです。
AIの学習機能を使えば、候補者のスキルや実績をある程度定量化できます。
定量化したデータを元に、一定基準をクリアした候補者のみ二次選考に進める、といった使い方が可能です。
また、AIに過去の合格者情報を学習させることで、マッチする人材を絞り込むこともできます。
社内で活躍している人材と似た特徴・スキルを持っていれば、採用後の働きぶりもイメージしやすいでしょう。
AIの採用予測は求める人材の採用に最適ですが、その他にもたくさんのメリットがあります。AIを採用に活用するメリット
AIを採用予測に使うメリットとして、効率化と公正性が挙げられます。
まず、AIを使うことで採用を効率化できます。特に書類選考においては、膨大な応募書類1つ1つに目を通して判断しなければなりません。
応募者が増えれば増えるほど人事担当者の負担も増え、採用にかかる時間は膨大になります。ですがAIを採用に活用すれば、かなりの効率化・時短が可能です。次に、AIを使うことで選考の公正性が担保できます。
人事担当者は採用のプロですが、人である以上、主観が入り込む可能性はぬぐいきれません。
候補者の学歴や過去の採用経験など、あらゆる面で人事担当者の主観が入る可能性があります。
経験に裏付けられた主観も必要ですが、行きすぎると担当者によって合否が異なるという事態も起きかねません。
こうした採用基準の属人化も、AIを使えば一定の基準で候補者を判断できます。
選考の公平性が保てるのは、企業にとっても候補者にとってもメリットの1つといえます。なお、採用選考をAIに完全に任せている会社はまだ少ないです。
AIで候補者の絞り込みを行った後、最終的には人が判断を下すことが一般的になっています。 -
AIを活用した採用予測の事例
実際にAIを採用予測に使っている会社の事例をご紹介します。
・大手通信キャリア
・大手飲食チェーン店大手通信キャリアの事例
大手通信会社では、新卒社員の選考にAIを導入しています。
具体的には、ES(エントリーシート)選考と動画面接でAIが活用されています。
AIにはまず、インターンシップ選考時の動画データと、人事担当者の過去の評価データを学習させます。
データを学習をしたAIが、ESの内容や動画面接の様子から自動で評価を算出し、合否を判定するという仕組みです。
なお、こちらの企業ではAIが完全に合否を決定しているわけではありません。
AIが不合格と判定した場合は人事担当者が動画を確認し、最終的な合否判断をしているようです。
AIを採用予測に活用したことで、こちらの企業ではES選考にかかる時間を約75%削減することに成功しました。
加えて、新型コロナウイルス感染拡大の影響下でも安全に選考が行えるというメリットもあります。
そのため、当面はAIによる採用予測を活用していく方針を発表しています。大手飲食チェーン店の事例
AI面接を導入している意外な企業が、大手飲食チェーン店のアルバイト面接です。
一般的なアルバイト面接は、店舗責任者が行うことが多いでしょう。ですが、こちらの企業では責任者による面接とAIによる面接を併用しています。
AIが面接を行うことで、応募者のスケジュールに合わせて面接日程が調整できる他、店舗責任者の負担を軽減できます。
応募者は応募時に店長面接かAI面接か選択できるため、AI面接が嫌な場合は通常の面接も選択可能です。
導入当初はAI面接時の録画を確認していたようですが、現在では一定基準をクリアしている場合はAIの判断をそのまま採用しています。
応募ハードルを下げること、工数を削減することの2点が成功したため、導入店舗を徐々に増やしているとのことです。 -
AIを活用して採用予測をする方法
様々なメリットがあるAIの採用予測。
とはいえ導入しようにも、簡単に導入できるものなのか、何が必要なのかわからない方が大半ではないでしょうか。
AIを採用予測に使うには、プログラミングスキルや開発資金が必要な場合や、現場に導入するまでに工数がかかる場合がほとんどです。
場合によっては、採用予測向けにAI自体を共同開発が必要な場合もあります。
プログラミングできる人材がいない、時間も最小限にとどめたい。
そんな方には、AI活用プラットフォームの「MatrixFlow」がおすすめです。MatrixFlowとは?
MatrixFlowとは、プログラミングなしでAIを活用できるプラットフォームです。
用途に合わせてAIの構築から運用までできるプラットフォームになっています。
具体的には売上予測や在庫予測の他、文章やテキストの意味を理解し、分析することも可能です。
そのため、採用領域においてはESや履歴書といった一次選考に活用できます。
また、募集要件や過去の選考データをAIに学習させれば、さらに高度な採用予測も可能です。
例えば、選考で高評価を得る候補者を予測したり、AIが企業にマッチする人材をレコメンドすることもできます。
求める役割や部署ごとに人材要件を変えられるため、様々なニーズに応えられます。
なお、MatrixFlowでは、AIを構築・運用するのにプログラミングスキルは一切不要です。
画面上で視覚的に操作するだけで、求めるAIを作ることができます。
もちろん、導入支援や過去の活用事例も豊富にあるため、採用課題から共にAIをデザインできます。具体的なAIの構築方法

具体的には、どのような手順でAIを構築していくのでしょうか。
最初に、AIで解決したい採用課題を定義します。ここでAIに求める機能を大まかに考え、必要なデータを洗い出し、AIを構築していきます。
MatrixFlowではボタンやマウスの操作だけでAIの構築ができ、アルゴリズムと呼ばれる「どのような手順でアウトプットを出すのか」といった選択も自動化されています。
AIに関する知識はもちろん、機械学習やプログラミングの経験はいりません。
なお、今回は採用に焦点を当てていましたが、AIを活用した離職率の改善や最適な人員配置も可能です。
勤怠データ等から数ヶ月以内に退職の可能性がある人物を予測したり、適性から最適な部署・ポジションはどこか判定させることもできます。 -
AIを活用した採用予測 まとめ
・AI採用とは書類選考や面接をAIが行うこと
・人材要件や過去の合格者データをAIに学習させることが可能
・AI採用には採用のマッチング率向上・効率化・公平性の担保といったメリットがある
・大手通信会社や飲食店の書類選考・面接での導入実績もある
・AIを活用した採用予測ならMatrixFlowがおすすめAIを使った採用予測とは何か、できることやメリットをご紹介しました。
AIを活用すれば採用後のミスマッチ防止や工数削減など、様々な採用課題の解決が可能です。
実際に、大手企業の一部では既にAIを採用に導入しています。
AI採用の導入にはプログラミングスキルや導入までの期間がネックですが、AI活用プラットフォームならその課題を解決できます。
AI活用プラットフォームであるMatrixFlowでは、プログラミングスキル不要、短期間でAIの構築から運用までが可能です。
解決したい採用課題からAIの構築をサポートしてくれるため、自社課題にマッチしたAIを作ることができます。
編集部Pickup記事
-
![]()
ノーコードでAIを開発する方法とは?開発事例・無料の開発プラットフォームを紹介
ここ数年、国内外の開発者の間で「ノーコード(NoCode)」という言葉がよく聞かれます。 ノーコードとは、文字通りコードいらずでWebサイトやWebサービスを開発する手法のことです。 このノーコードの開発手法を使って、AI(人工知能)を開発しようとする動きが出てきています。 本記事では、ノーコードでAIを開発して自社課題を解決したい方に向けて、ノーコードでどんなことができるのかを解説していきます。 ノーコードを使ってAIを開発した事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
-
![]()
機械学習のビジネスにおける活用事例を徹底解説
様々な分野・企業で、AIや機械学習の活用が進んでいます。 iPhoneのSiriやGoogleのアレクサなど、日常生活にも溶け込んでいるほどです。 AIにデータを機械学習させれば、膨大な時間がかかる作業も分析も一瞬で終えることができます。 AIは学習させるデータでどんな使い方もできるため、その可能性は無限大です。 本記事では、AIや機械学習をビジネスに活用する方法や、導入事例をご紹介します。
-
![]()
AIツール・開発プラットフォームおすすめ13選!無料AIツールも?
AI(人工知能)を使ったツールやアプリは、ここ数年で急激に増えました。身近なところだと、有名画家風のイラストが作成できるアプリや音声読み上げソフトなど、一度は耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。 企業においても課題解決ができるAIツールや、AIを開発できるプラットフォームへ注目が集まっています。ですが、AIツールと一口にいっても、開発できるAIの種類や解決できる課題も様々です。 本記事では、AIを開発できるプラットフォームや、無料で使える便利なAIツールをご紹介します。AIツールを使ってどんなことができるのか、ツールによる違いを知りたい方は必見です。
-
![]()
AIによる需要予測の仕組みとは?導入事例・費用・アルゴリズムを解説
過去の販売データを元に商品の発注数や売れ行きを予測するのは、小売業界では当たり前に行われています。 ですが、経験や勘に頼った予測は個人の力量に依存するため、予測に再現性がありません。予測の精度も人によってバラバラなため、常に高い精度で予測することは難しいです。 こうした課題を解決する方法の1つとして、AIを使った需要予測が注目されています。AIを使うことで、スキルに依存しない高精度で需要予測が期待されているのです。 本記事では、AIを使った需要予測の仕組みや導入事例について解説していきます。需要予測をして在庫管理の最適化や売上増加を狙っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
-
![]()
製造業におけるAI活用事例23選!各社の導入方法・例をご紹介
ここ数年でAi技術は格段に進化を遂げています。様々な領域でAIの活用が進んでいますが、製造業ではどのくらいAIの導入が進んでいるのでしょうか。製造現場での実用化にはいまだ課題も残っています。AIを活用できる人材がいない、AIの導入方法がわからず、活用が進んでいない企業も多いのではないでしょうか。 この記事では、実際にその仕組みや導入のメリット、成功・失敗事例を紹介していきます。製造業でAIを導入するうえでの注意点についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
-
![]()
ディープラーニング(深層学習)とは?AI・機械学習との違いを簡単に解説
ディープラーニング、AI、機械学習。誰しも、テレビや本で一度は耳にしたことがあると思います。 ですがこれらが何を指しているのか、なぜ注目を集めているのか知っている方は少ないのではないでしょうか。 本記事ではAIを学んだことがない方向けに、ディープラーニングとは何なのかを簡単に解説します。 ディープラーニングと機械学習の違いがわからない方や、ディープラーニングの活用事例を知りたい方も必見です。
関連した事例
-
![]()
予測分析ツールおすすめ7選比較!AIで予測できること・無料ツールはある?
将来の売上や株価を予測することができれば、ビジネスや投資において非常に有利に動けます。しかし、人の勘や経験に頼った予測には限界があり、正確な予測をすることは困難です。 そこで、あらゆる業界で「予測分析ツール」が注目されています。予測分析ツールを使えば、膨大なデータを分析し、過去の傾向をもとに未来を予測できます。さらに、機械学習や人工知能を使った予測分析ツールを活用すれば、誤差を減らしてより高い精度で予測を行うことができます。 本記事では、予測分析ツールでどんなことが予測できるのか、おすすめの予測分析ツールをご紹介します。AIやツールを使った予測に興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
-
![]()
AI開発外注の費用相場・期間は?おすすめ開発会社を解説
AIを開発したいと思った時にまずぶつかる壁は、「自社内で開発するか外注するか」です。 社内に開発人材がいる場合もいない場合も、AI開発の外注は選択肢の1つとして考えられます。 AI開発の外注にはメリット・デメリットがあるため、AI開発において重視する内容によって外注が最適かどうか変わってきます。 本記事では、AI開発を外注しようか検討している方に向けて、AI開発の外注にかかるコストやメリット・デメリットを解説します。さらに、AI開発に強いおすすめの外注先もご紹介するので、開発会社選びの参考にしてみてください。
-
![]()
AIツール・開発プラットフォームおすすめ13選!無料AIツールも?
AI(人工知能)を使ったツールやアプリは、ここ数年で急激に増えました。身近なところだと、有名画家風のイラストが作成できるアプリや音声読み上げソフトなど、一度は耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。 企業においても課題解決ができるAIツールや、AIを開発できるプラットフォームへ注目が集まっています。ですが、AIツールと一口にいっても、開発できるAIの種類や解決できる課題も様々です。 本記事では、AIを開発できるプラットフォームや、無料で使える便利なAIツールをご紹介します。AIツールを使ってどんなことができるのか、ツールによる違いを知りたい方は必見です。
-
![]()
ノーコードでAIを開発する方法とは?開発事例・無料の開発プラットフォームを紹介
ここ数年、国内外の開発者の間で「ノーコード(NoCode)」という言葉がよく聞かれます。 ノーコードとは、文字通りコードいらずでWebサイトやWebサービスを開発する手法のことです。 このノーコードの開発手法を使って、AI(人工知能)を開発しようとする動きが出てきています。 本記事では、ノーコードでAIを開発して自社課題を解決したい方に向けて、ノーコードでどんなことができるのかを解説していきます。 ノーコードを使ってAIを開発した事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
-
![]()
プログラミングでAIを開発する方法!必須のプログラミング言語・入門知識を解説
近年急速に進化しているAI(人工知能)。 AIを活用すれば、今まで大量の人と時間を投下していた業務も効率よく精度高く遂行できます。 人と同じような動きができるためすごい存在に思えるAIですが、プログラミングを学べば初心者でも開発が可能です。 本記事では、プログラミングをしてAIを開発する方法やAI開発におすすめのプログラミング言語をご紹介します。
-
![]()
機械学習(ML)とは? メリット・種類・業界や課題別の活用例・実施方法を解説
機械学習(Machine Learning)とは、コンピューター(Machine)が与えられた大量のデータを処理・分析することでルールやパターンを発見する技術・手法のことです。学習の結果明らかになったルール・パターンを現状に当てはめることで、精度の高い将来予測が可能となります。 高度なコンピューターを使用することで、人間の脳では処理しきれない複雑な要素を加味した分析・学習が可能となりました。その結果、近年ではさまざまな領域において人間による作業の精度向上・効率化に役立てられています。自動運転や医療、人間の購買行動の分析など、さまざまなビジネス領域で機械学習が実用化されており、今後のマーケットで生き残っていくためには必須の技術になりつつあるといえるでしょう。 本記事では、機械学習(ML)の概要やメリット、種類に加え、業種別・課題別の活用例を紹介します。実際に取り入れる際の作業フローも紹介しているので、機械学習の活用に興味がある方はぜひ参考にしてみてください。
-
![]()
データドリブン経営とは?成功事例からわかる必要性・メリット解説
ビジネスでデータを活用するのは、今やどの企業も当たり前に行なっています。 ですが、データを効果的に活用できている企業はあまり多くありません。 データを部分的にしか活用できていない、人によってデータ活用のレベルが異なる企業が多いのではないでしょうか。反対に、データを活用しようと意気込んで収集した結果、膨大なデータを持て余している場合も見受けられます。 このように、データを有効活用できていないと感じる方々に知っていただきたいのが、「データドリブン経営」という考え方です。本記事では、データドリブン経営とは何かを簡単に解説し、データドリブンで数字改善した成功事例をご紹介します。データを活用して売上を伸ばしたい、コスト改善したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
-
![]()
AIやExcelを活用したコールセンターの入電数予測の方法
コールセンターにおけるコール予測(呼量予測、forecaster)とは、お客様からの問い合わせなどセンターで受信する電話の量を予測することをいいます。 コールセンターの運用コストを増加させる要因のうち大きなものが、コミュニケーターの人件費です。コミュニケーターは顧客からの入電に応じてオペレーションの対応をするため、実際の入電数よりも多くのコミュニケーターを配置すると、対応がなく待ち状態のコミュニケーターが増えて、不要な人件費の増加に繋がります。また、逆に配置人数が少ないと呼び出し中でつながらないなどのクレームの要因になりかねません。適正な人員をコンタクトセンターに配置することで、十分な顧客満足度が提供できる状態でオペレーションを行っていることが理想です。今回は、Excelを活用したコール予測、AI(人工知能)による機械学習を用いた時系列分析で、コール予測を実現する方法をご紹介します。
-
![]()
予測分析とは?活用事例とその手法・ツールをご紹介
予測分析とは、過去の行動パターンを特定し、将来の結果を予測するために、大量のデータに数理モデルを適用する手法です。 機械学習、データマイニング、統計アルゴリズムなどの複数の組み合わせがもたらす「予測的手法」により、予測分析ツールは、単純な相関付け以上の機能を実装できます。ビジネス分野では、予測分析が以下に示すようなさまざまな用途に利活用されています。 ・需要と供給のより正確な予測コンピューターネットワークに悪影響を及ぼす脅威と潜在的問題の特定 ・保険サービスや金融サービスにおけるセキュリティリスクの低減 ・クレジットカード詐欺のリアルタイム検出 予測分析機能を組み込んだソフトウェアが増えつつあり、これはあらゆる規模の組織体でユーザーにとって身近なものになっています。予測分析はデータサイエンスや高度な分析に関する訓練を受けていないエンドユーザーにも実務上の価値をもたらします。これは、まさにすべてのユーザーが恩恵を受ける機会を提供することに値します。この概念を「データの民主化」と呼びます。誰もがデータを利用してより良い意思決定を下せるように、組織全体でデータを誰もが利用できるようにするという概念です。 本記事では、予測分析がなぜ重要なのか、予測分析の実活用例、予測分析の手法、機械学習やデータマイニングなどの他のテクノロジーとの関係、モデルの役割、予測分析を始めるにあたってのヒントについてご紹介します。